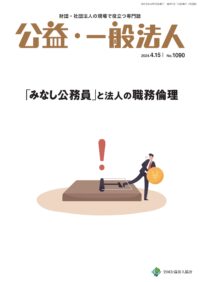「寄附を推進力に」と指定正味財産規制
2022年11月22日
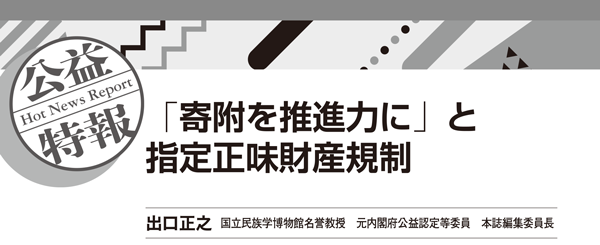
指定正味財産とは何か
令和4年10月4日付けで「寄附を推進力に」が内閣府により公表された。財務三基準の考え方の誤解の大きな要因となっていることとも深い関係があるので、関連情報も含めて説明したい。指定正味財産は、もともとは米国のコミュニティ財団等が寄付調達のために創設し、発達したものである。そうした実態を会計的に表現するために、FASB(Financial Accounting Standards Board 米国財務会計基準審議会)が、非拘束資金、一時拘束資金、永久拘束資金としたもの(当時。現在は2分類)を参考に、平成16年公益法人会計基準にて日本に導入された。その際、分類を2つにし、用語も「拘束」というのがいかにも強すぎるということで、「一般正味財産」、「指定正味財産」となった。なお、米国でこの記事は有料会員限定です。