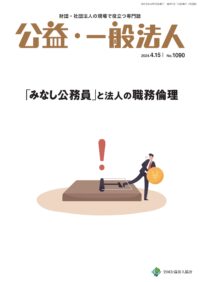FAQ改正、別表Hの解説を追記
2022年04月21日

3月30日、内閣府公益認定等委員会事務局は「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」を追加・修正した。
追加されたFAQは6つ(問VI-6-1~6)、修正されたFAQ(問VI-4-8、9)は形式的な修正であった。追加された内容は、令和3年6月に別表Hが変更されたことに伴う「定期提出書類の手引き公益法人編」の改訂を補完する内容である。以下に追加項目の全文を掲載する(本紙編集部:後藤沙織)。公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)内閣府公益認定等委員会事務局
別表Hとはどのようなものですか。答
1 公益法人は、毎事業年度の経過後3カ月以内に財産目録等を行政庁に提出しなければなりません(認定法第22条第1項)が、その様式第5号による提出
追加されたFAQは6つ(問VI-6-1~6)、修正されたFAQ(問VI-4-8、9)は形式的な修正であった。追加された内容は、令和3年6月に別表Hが変更されたことに伴う「定期提出書類の手引き公益法人編」の改訂を補完する内容である。以下に追加項目の全文を掲載する(本紙編集部:後藤沙織)。公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)内閣府公益認定等委員会事務局
【追加】
問VI-6-1(別表H)別表Hとはどのようなものですか。答
1 公益法人は、毎事業年度の経過後3カ月以内に財産目録等を行政庁に提出しなければなりません(認定法第22条第1項)が、その様式第5号による提出
この記事は有料会員限定です。